2027年からのレギュレーション刷新、そして「企業の意思」
2022年、スズキは突如としてMotoGPからの撤退を発表した。スズキ100周年となった2020年にはジョアン・ミルがタイトルを獲得し、アレックス・リンスも2022年に複数の勝利を挙げるなど、戦闘力を備えたファクトリーチームだっただけに、その決断はパドックに衝撃を与えた。
以来、MotoGP界隈では「スズキ復帰」の噂がたびたび浮上するが、確かな情報は一切出ていない。しかし2027年、排気量が850ccへ縮小される新レギュレーションの導入が予定されており、これを機にスズキが再びグリッドに戻ってくる可能性がゼロではないという声もある。
果たしてそれは現実的なシナリオなのか、それともただの希望的観測に過ぎないのか。
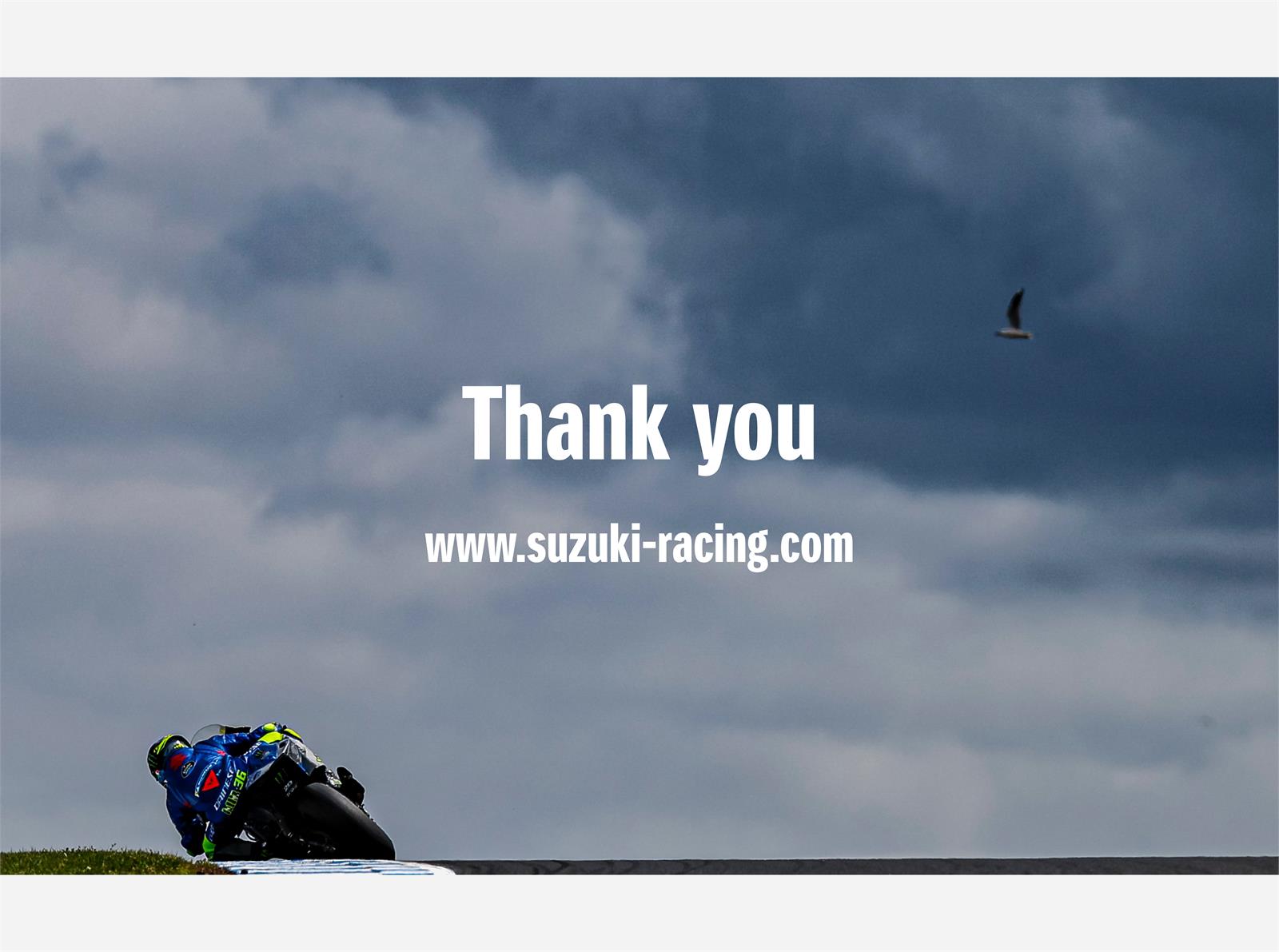
勝てるチームがなぜ去ったのか
スズキの撤退は成績不振によるものではない。2020年にはミルがチャンピオンを獲得し、2021年以降も一定の戦闘力を維持していた。しかし、レース部門に投じられていた資金と人的リソースを、EV車両や次世代モビリティ開発といった将来分野に振り向けるという本社方針が下され、MotoGPを含むすべての二輪レース活動からの撤退が決まった。
現場には事前の共有がなく、関係者にとってはまさに寝耳に水だったとされる。ファクトリーとしてのスズキMotoGPプロジェクトは、競争力を持ったまま突如として消滅した。
海外の反応と再参戦への期待感
スズキの撤退は欧州メディアでも大きく取り上げられたが、2023年以降、復帰に向けた確かな動きは確認されていない。英語圏の媒体では、「復帰には最低2年の準備が必要」としながらも、「現時点で開発プロジェクトが動いている形跡はない」と報じている。
一方、MotoGP人気が根強いスペインやイタリアでは、より感情的な論調が目立ち、「850cc新時代こそスズキにとって理想的な復帰タイミングだ」とする期待論も見られる。だが、それらはあくまで外野の希望的観測にとどまっており、具体的な証拠を伴う報道は存在しない。
850cc新レギュレーションは「再出発」の好機か?
2027年に導入予定のMotoGP新レギュレーションでは、排気量が現行の1000ccから850ccへと縮小される。この変化は単なるエンジンサイズの変更にとどまらず、環境対策、エアロダイナミクスの規制、ホールショットデバイス、ライドハイトデバイスの禁止など、マシン開発全体の再編を含んでおり、事実上の“リセットボタン”といえる。
このような大規模なルール変更は、過去にも新規参戦や再参戦のきっかけとなってきた。ApriliaはCRT時代を経てファクトリー体制を確立し、KTMも2017年に本格参戦して以降、表彰台争いに絡む位置まで登り詰めた。スズキにとっても、再び“ゼロから”プロジェクトを立ち上げる好機に見えることは間違いない。
しかし、現実に復帰の兆候は見られない
だが、復帰を可能にするためには、早期からの準備が不可欠だ。エンジンや車体の設計、テスト体制の構築、ライダー選定に至るまで、MotoGP参戦には少なくとも2年のリードタイムが必要とされる。すなわち、2027年の参戦を目指すのであれば、2025年の時点で具体的なプロジェクトが立ち上がっていなければ間に合わない。
ところが、2025年現在、そうした動きは一切見られない。社内関係者からの明確な示唆もなければ、外部への情報漏れもない。かつては、竜洋テストコース周辺でMotoGPマシンのような特徴的な排気音が聞こえたという報告がX(旧Twitter)上で散見されていたが、2023年以降、そうした情報は途絶えているようだ。
スズキの企業哲学と二輪レースの未来戦略
スズキのMotoGP撤退の背景には、「費用対効果」の観点からレース活動を見直すという明確な企業方針がある。これは一時的な方針ではなく、IR資料と中期経営計画(2023~2025)に基づいた組織戦略の転換である。
スズキが現在注力しているのは以下の領域だ:
- 電動車両(EV・ハイブリッド)開発への集中投資
- インド市場における四輪・二輪の現地生産体制強化
- ソフトウェア開発とコネクテッド技術の内製化
- 次世代電池(全固体電池など)への共同研究
- 自動運転・ADAS技術におけるトヨタとの連携強化
これらはいずれも、グローバル市場での成長や収益確保に直結する分野であり、レース活動のような純コスト領域とは対極にある。 スズキのように効率経営を重視する中堅企業にとって、MotoGPのような高コストで直接的リターンの見えにくい投資は優先度が著しく低くなる。
実際、2022年の撤退決定は経営陣レベルで迅速に下された。このような明確な方針転換が、わずか数年で再び逆転する可能性は極めて低い。
結論:「企業としての意思」が鍵を握る
スズキのMotoGP復帰の可能性を論じる上で、最大の論点は技術力や人材の有無ではない。企業として、再びレース活動に戦略的価値を見出すかどうか?その「意思」がすべてである。
実際、2025年2月に発表された新中期経営計画「By Your Side」では、2030年度に売上収益8兆円、営業利益8000億円(営業利益率10%)を目指すことが明記され、四輪・二輪ともに成長戦略の中心にあるのはBEV(電気自動車)やハイブリッド、そして新興国戦略だ。
四輪では日本で2025年度に「eビターラ」や軽商用バンのBEVを投入し、2030年までにBEV6モデルを展開予定。インドでは2030年度までにBEV4モデルを投入し、同国シェア50%維持を狙う姿勢も鮮明だ。一方で、二輪事業も販売台数254万台、営業利益500億円という堅実な目標設定となっている。
加えて、新規事業領域としてサービスモビリティやエネルギー領域に注力し、2040年度までに「既存事業に並ぶ収益の柱」に育てるという意思がある。全体的に、スズキの経営資源は「レース」ではなく「持続可能な成長と環境技術」に投下されているのが明白だ。
もしMotoGP再参戦のような大規模かつ高リスクなプロジェクトを開始するのであれば、それは現行の経営戦略との根本的な乖離を意味する。その場合、当然ながら株主や市場への説明責任が発生し、今回発表された2030年までの中期経営計画に何らかの形で明記されている必要があったはずだ。
現時点で、そのような兆候は一切ない。今後、発表されるであろう将来の経営計画においてもレース活動への言及がなければ、スズキのMotoGP復帰は中期的には完全に選択肢から外れていると結論づけるほかない。850cc新時代が迫るなか、グリッドにスズキのエンブレムが再び並ぶ可能性は、今のところ極めて低いと言えるだろう。
(Photo courtesy of suzuki)

中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。